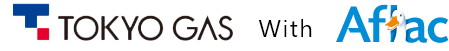目次
これから定年退職を迎える50代・60代の方は、定年後の生活について、さまざまな疑問を抱えているでしょう。
この記事では、定年退職後の生活を充実させるための方法や、必要な準備、ストレスフリーかつ有意義に暮らすための注意点を解説していきます。「第二の青春」ともいえる定年後の生活をより良きものにするために、ぜひお役立てください。
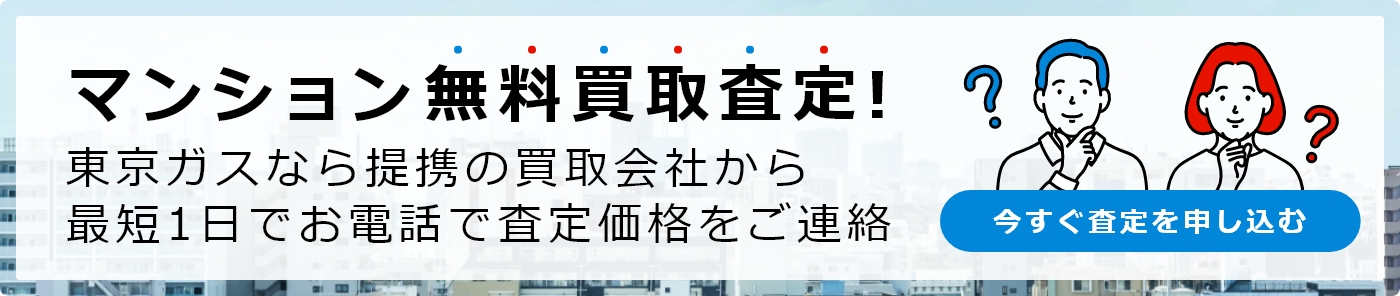
・定年後の生活を充実させる方法
・定年後の生活を充実させるための準備
・定年後の生活の注意点
定年後の生活を充実させる方法
定年後の生活を自分らしく充実したものにする方法として、次の3つを紹介します。
- 趣味を見つけて楽しむ
- 食事・運動など健康を意識した生活を送る
- 楽しめる交流関係を築く
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
趣味を見つけて楽しむ
夢中になる趣味を見つけて、日々の生活に刺激や喜びをプラスすると良いでしょう。趣味は、ただ単に時間をつぶすものではなく、心ゆくまで楽しむことで人生をより豊かで意味深いものにしてくれます。「今からでもまだ挑戦できることがある」というポジティブな気持ちも持てます。
ずっと興味があったことや、時間がなくてできなかったことに挑戦してみましょう。例えば、次のような趣味はいかがでしょうか。
- アウトドアや旅行
- 写真や音楽
- 読書や映画鑑賞
- ガーデニング
- 料理
- ウォーキングなどの運動
- ボランティア活動
趣味を通して新しいスキルを習得することは、脳を活性化させたり、達成感を得たりできるメリットがあります。無理なく取り組める範囲内で、自分の好きなことを楽しむ時間を持ちましょう。
食事・運動・睡眠など健康を意識した生活を送る
健康で活動的に生きられる期間(健康寿命)を延ばすためには、適度な運動と良質な睡眠が不可欠です。また、暴飲暴食に注意し栄養バランスの取れた食事を摂ることも必要です。
こうした生活習慣の改善は、単に長生きするだけでなく、定年後の生活をいかに充実して過ごせるかにも大きく影響します。
厚生労働省は、高齢者の健康づくりについて、以下の点を推奨しています。(※1)
- 【運動】有酸素運動や筋力トレーニングなどの運動を週3回以上行う
- 【睡眠】床上時間が8時間以上にならないよう、適切な睡眠時間を確保する
また、高齢期の食事については、「孤食」が引き起こすリスクも懸念されています。孤食とは一人で食事を摂ることですが、一人暮らしでない場合でも家族とは別に食事をするケースが見られます。
高齢者が孤食をすると、欠食や肥満、低体重、うつなどになるリスクがあるという研究結果もあるため、可能な限り孤食を避けるのもポイントです。
健康診断や人間ドックなどを定期的に受け、日頃から健康的な生活を送ることで、定年後も心身ともに元気に過ごせるでしょう。
楽しめる交流関係を築く
定年後は、気兼ねなく付き合える人たちと過ごす時間を大切にすると、充実感を得やすくなります。現役時代は仕事上のしがらみもあり、交流関係にストレスを感じる人も多いですが、定年後は交流関係を自由に構築することが可能です。
例えば、次の点に重きを置いた交流関係を築くと良いでしょう。
- 関心のある分野に共通点がある
- 無理をせずに同じ時間を過ごせる
- 一緒に趣味を楽しめる
交流関係は「社会とのつながり」ともいえます。定年を迎えて自由な時間が増えても、社会とのつながりを失ったり生きがいを見つけられなかったりすると、老後の生活は味気なく感じられやすくなります。
現役時代には当たり前だった交流関係が、定年後も続くとは限りません。地域のコミュニティに積極的に関わってみるのも一案です。ただし、ストレスを抱え過ぎないことを心掛け、楽しく過ごせる交流関係を築きましょう。
定年後の生活を充実させるための準備
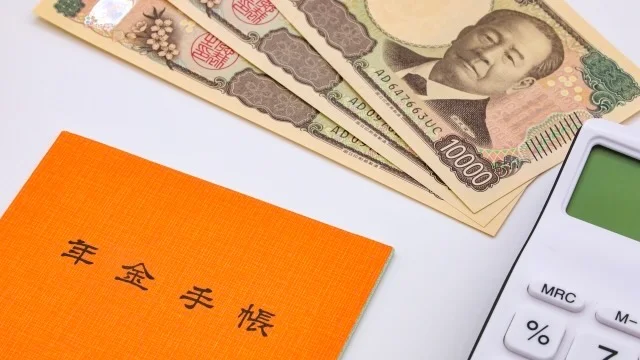
定年後の生活を心豊かなものにするためには、お金に関する不安や悩みを払拭することが重要です。
まずは定年後の生活にかかる具体的な生活費を把握しましょう。そのうえで、不足する分を補填する方法を考えていきます。
定年後の生活資金を確認する
定年後の主な生活資金は、公的年金や私的年金などになることが多いです。具体的には、以下のものが該当します。
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 個人年金保険
- 貯蓄や投資などの個人資産
公益財団法人 生命保険文化センターが行った調査によると、老後における夫婦2人の最低限の生活費は平均23万2,000円です。一方、ゆとりある生活を送るためには、37万9,000円が必要だとされています。
しかし、総務省統計局が発表した「家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の無職世帯の実収入は以下の通りです。(※2)
| 65歳以上の無職世帯 | 実収入 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 65~69歳:30万7,741円 70~74歳:27万5,420円 75歳以上:25万2,506円 |
| 夫婦のみの世帯 | 25万2,818円 |
| 単身世帯 | 13万4,116円 |
この調査結果からは、定年後にゆとりのある生活を送るためには、何らかの形で収入の上乗せが必要であることが分かります。
まずは自分が定年後に受給できる年金額や資産額を確認したうえで、上乗せが必要な金額を計算することが大切です。
なお、将来の年金受給額を確認する方法として、「ねんきんネット」や「公的年金シミュレーター」、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」があります。
資産運用で定年後の生活資金を増やす
定年後の生活を豊かにするには、年金収入だけでなく、資産運用で資金を増やすことも選択肢のひとつです。
現役時代であれば、毎月コツコツ貯蓄することも可能ですが、定年後は今ある資産を活用し、増やす方法を取り入れる方が現実的でしょう。現在、日本では低金利が続いており、老後資金を形成するだけの利息は期待できないためです。
老後の生活資金を形成するためには、以下のような資産運用方法があります。
- 株式投資
- 投資信託
- 債券投資
- NISA
- iDeCo
原則として、株式や債券投資、投資信託などから得られた利益に対しては、所得税や住民税がかかります。しかし、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を利用すれば利益が非課税になるため、効率よく定年後の生活費を準備することが可能です。
ただし、資産運用には為替リスクや価格変動リスクなど多様なリスクがあり、元本が保証されているわけではありません。そのため、定年後の生活資金を増やすために資産運用を活用する際は、リスクについて十分に理解し、目的やニーズに合った方法を選ぶことが重要です。
持ち家の売却を検討する
定年後の生活費を補填する方法として、持ち家を売却する方法もあります。自宅を現金化することで、老後の生活費だけでなく医療費や介護費用といった出費に充てられます。
また、持ち家を手放すことで、固定資産税や都市計画税などの税金の納付義務がなくなり、出費を抑えることも可能です。
売却で得られた資金をもとに、高齢者にとって利便性の良い場所やバリアフリーの住居へ住み替えることで、生活の質を向上させることも可能になります。
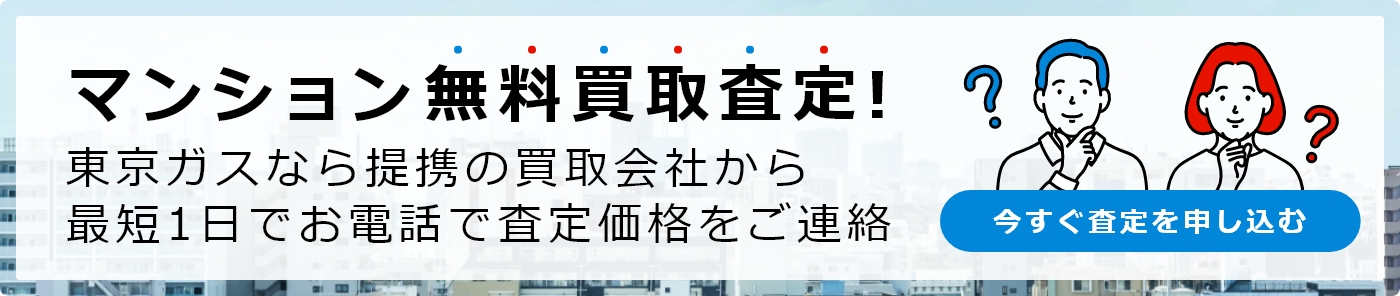
定年後の生活の注意点

定年後の生活を、有意義かつストレスフリーにするために、次の点に気を付けましょう。
- 限られた人間関係に固執しない
- 適度な運動を心掛ける
- 資産運用のリスクを理解する
- 無理をせずに働く
- ストレスのかかる住まいは避ける
ひとつずつ確認していきましょう。
限られた人間関係に固執しない
定年後は、これまでの人間関係に捉われず、新たな出会いにも目を向けると良いでしょう。できれば現役時代のうちから、仕事関係以外の知人や友人を作っておくのがおすすめです。
現役時代の気心が知れた仲間と、昔話に花を咲かせる時間は心地よく貴重なひと時です。一方で、老後に向けた新しい人間関係を築く機会を失ってしまう可能性があります。
定年後の生活をともに過ごす友人・知人を作るためには、趣味や地域のイベントなどに積極的に参加するのも一案です。視野を広げて積極的に新しい出会いを見つけ、多様な人と知り合い、新たな人間関係を作っていくことが、定年後の充実した生活につながるでしょう。
適度な運動を心掛ける
先にも触れたように、定年後の生活を充実させるには適度な運動を習慣付けることが大切です。
以下のような身体的・精神的な機能の低下は、年齢を重ねるうえで避けられないものです。
- 体重減少
- 筋力低下
- 倦怠感、疲れやすさ
- 歩行速度の低下
しかし、こういった状態になったからといって運動を避けると、機能の低下はさらに進行し、自立して日常生活を送ることが困難になる可能性があります。日々、適度な運動を心掛けておけば、加齢によって低下する身体機能を活発にし、定年後の健康寿命を延ばすことにつながるでしょう。
なお、健康な状態と介護が必要になる状態の間を「フレイル」といい、病気のリスクが高まる時期とされています。定年後の生活を健康的に送るためには、適度な運動や栄養バランスの良い食事、適切な睡眠時間を心掛けることが、病気やケガの予防につながります。
資産運用のリスクを理解する
退職金などのまとまった資金が手に入った際、投資経験のない方が未経験のまま、資産運用で大きな利益を得ようとすると、思わぬ損失を被る可能性があります。
資産運用には知識や経験だけでなく、投資特有の感情コントロールも必要です。そのため、知識や経験がない方が最初から高額取引をするのは、大きなリスクを伴います。
例えば、投資対象の価格が下落した場合、状況を見て損切り(※)することが大切です。しかし、慌てて損切りすると逆に大きな損失となるケースは少なくありません。
資産運用では、リターンとリスクは表裏一体の関係となっており、最新の経済状況の把握と客観的な予測が必須です。広い視野と経験による予測が必要な資産運用では、豊富な経験がなければ高額投資はリスクの高い行為だといえます。
投資の3原則である「長期・分散・積立」を常に意識し、退職金などを一度に投資に充てることは避けましょう。
※「損切り」とは、損失が出ている投資商品を売却し損失を確定させることです。
無理をせずに働く
定年後は、健康状態や家庭状況などを考慮し、無理のない範囲で働くことも選択肢のひとつです。内閣府が公表した「令和6年版高齢社会白書」によると、60歳以上の就業状況は以下のようになっています。(※3)
| 60歳以上の就業率 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 60~64歳 | 84.4% | 63.8% |
| 65~69歳 | 61.6% | 43.1% |
| 70~74歳 | 42.6% | 26.4% |
定年後も働くことで、老後資金の不足といった経済的な不安を軽減することが可能なうえ、生きる活力にも結びつくでしょう。また、規則正しい生活を送ることになるため健康維持にもつながるほか、新しい友人や知人を作る意味でも効果的です。
定年後の仕事として、以下のような職業が人気です。
- 飲食業
- 軽作業
- 接客業
現役世代の経験を活かせる仕事を探したり、起業に結び付く仕事を見つけたりするのもおすすめです。
定年したからといって家で過ごすだけが選択肢ではありません。無理はせず心身ともに健やかな状態で働くことを検討するのも良いでしょう。
ストレスのかかる住まいは避ける
定年後は以前より自宅で過ごす時間が長くなるため、過ごしやすい住まいを整えることが大切です。現在の住まいに何かしらの不満や問題を抱えている場合は、次のような方法でストレスのかからない住まいづくりをすることを推奨します。
- 立地条件のよい場所に引っ越す
- 老朽化した自宅はリフォームする
- バリアフリーの住居を探す
例えば、高齢になり足腰が弱くなると、階段がある戸建て住宅では昇り降りが困難になり、その結果1階部分しか使わない状態になりやすいです。また、自宅から病院や駅までが遠いと、外出をストレスに感じ、家にこもりがちになってしまうでしょう。
持ち家がある場合は、定年後のライフスタイルを考慮して、バリアフリーにリフォームしたり売却を検討したりするのも一案です。
ただし、持ち家を売却する際は、売却方法や依頼する業者も慎重に検討する必要があります。失敗のないよう、専門家に相談しながら定年前から検討することをおすすめします。
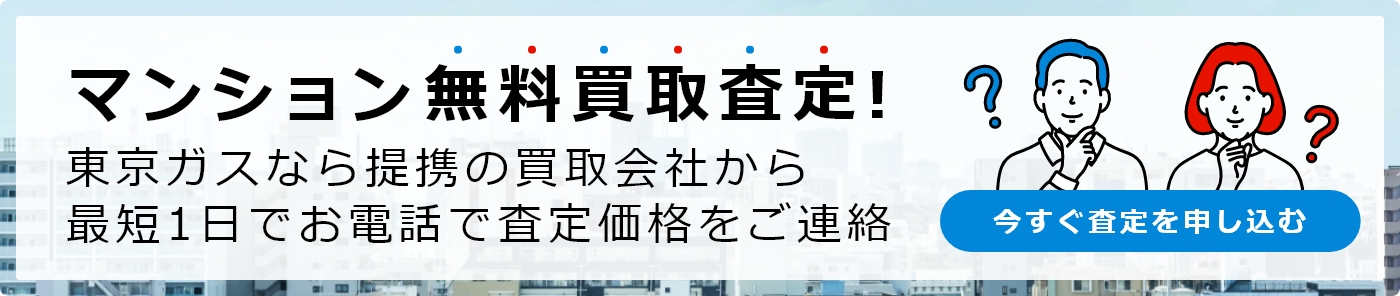
まとめ
自由時間の多い定年後の生活を待ち望んでいた方でも、実際に定年を迎えると、わずか数ヶ月でひまを持て余すケースが少なくありません。自由時間を確保できても、何も行動しなければ、充実した老後生活を送ることは難しいでしょう。
定年後の生活を快適なものにするには、健康を意識した生活を心掛け、楽しい交流や趣味を見つけることが大切です。そのためには、毎日の暮らしの拠点となる住まいの見直しも欠かせません。
老朽化した家や階段の多い住宅は年齢とともに不便さが増す傾向があるため、快適で利便性の高い暮らしを実現するには住み替えも一つの選択肢となります。
マンション買取サービスを利用すれば、専門家のサポートのもとスムーズな売却が可能です。詳しく知りたい方は、お気軽に東京ガスグループのマンション無料買取査定をお試しください。
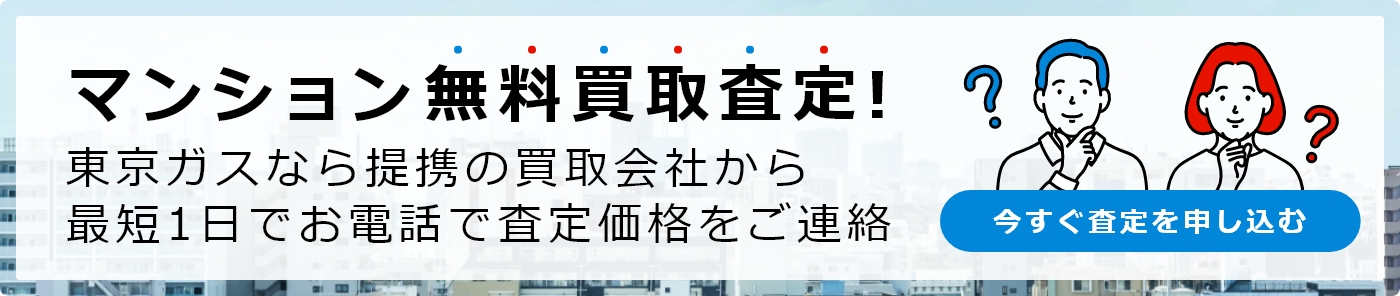
(※1)出典元:厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(案)
(※2)出典元:総務省統計局 家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要
(※3)出典元:内閣府 第1章 高齢化の状況(第2節 1)

 お金
お金