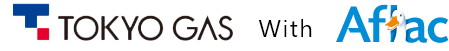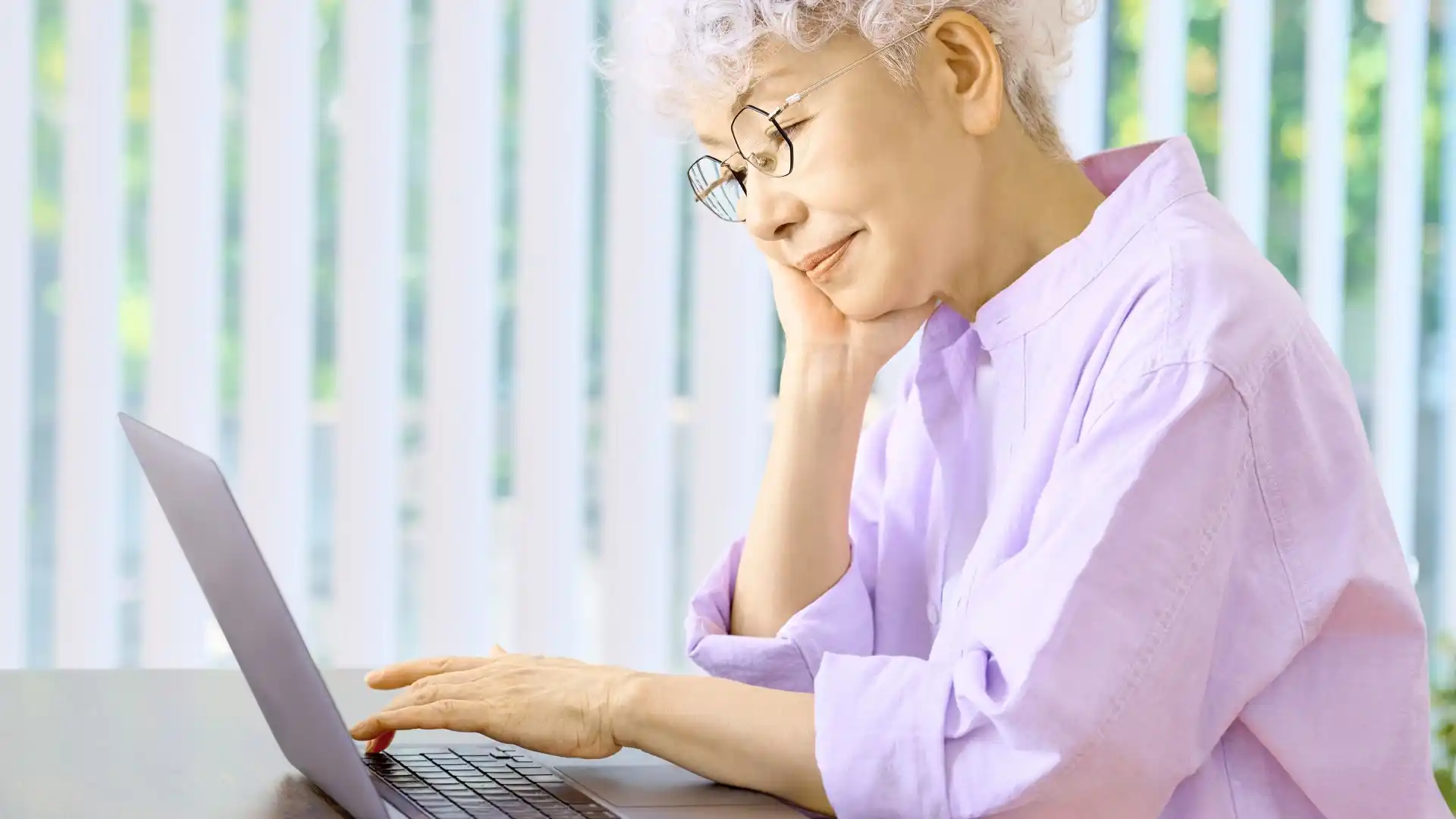目次
高齢者が施設に入所したり、賃貸物件を借りたり、就職したりする際には、身元保証人が必要になることが多いです。しかし、そもそも身元保証人とは何か、どんなときに誰に頼めばいいのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか
ここでは、身元保証人の役割や、必要になるケース、なれる人の条件、頼める人がいない場合の対処法まで、わかりやすく解説します。

・身元保証人の役割
・身元保証人が求められる場面
・身元保証人がいない場合の対処法
身元保証人とは?

身元保証人とは、本人の身元や社会的な信用を保証し、本人に代わって責任を負う立場となる人のことです。たとえば、入院する際や賃貸住宅を契約する際などに、手続きを代行したり、緊急連絡先になったりするほか、一定範囲内で金銭的な責任も担います。
そのため、もし本人が相手方に損害を与えたときには、身元保証人が本人に代わり賠償しなければならず、金銭的責任が発生するケースもあります。
このような理由から、知人や友人に対し、気軽に「身元保証人になって欲しい」と依頼するべきではありません。
身元保証人が求められる場面
高齢者が身元保証人を求められる場面として、主に以下の3つが挙げられます。
- 高齢者施設へ入所するとき
- 賃貸住宅の契約するとき
- 入院や手術の同意が必要なとき
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
高齢者施設へ入所するとき
有料老人ホームなど高齢者施設に入所する際には、身元保証人が必要になることが多いです。主な理由は次のとおりです。
- 支払いにおける経済的な保証のため
- 入居者が介護を要するようになったときの対応のため
- 入居者の判断能力が低下した場合の対応のため
- 施設との話し合いや相談に応じてもらうため
- 入居者が亡くなった際に遺留金品などを引き取ってもらうため
身元引受人の権利や義務は、入居する際に交わす契約書に記載されているのが一般的です。また、仮に身元保証人がいない場合は、入居を断られるケースがあります。
賃貸住宅を契約するとき
高齢者が賃貸住宅を契約する際にも、以下のような理由から身元保証人が求められます。
- 家賃を滞納した場合に代わりに支払ってもらうため
- 入居者が物件を損傷させた場合に代わりに修繕費を支払ってもらうため
身元保証人をたてることで、貸主は、入居者の健康上もしくは経済的な理由による費用不払いリスクに備えることができます。これにより、賃貸契約が円滑に進みやすくなります。
入院や手術の同意が必要なとき
高齢者が病気やケガで入院や手術をする際、以下のような理由により、病院から身元保証人を求められることが多いです。
- 主治医による治療方針を一緒に確認してもらうため
- 入院中に必要な物品の準備を依頼したいため
- 医療費を支払えない場合に支払いの相談をしたいため
- 万が一のときの緊急連絡先として身柄・荷物の引き受けを依頼したいため
近年は一人暮らしの高齢者が増加傾向にあることもあり、身元保証人がいない場合でも医療を受けられるケースが増えています。しかし、その際にはソーシャルワーカーへの相談を促されることが多いです。
身元保証人になれる人
身元保証人になれる条件は法律で明確に定められてはいませんが、一般的には安定した収入があることが求められます。というのも、万が一のときに本人に代わって責任を果たせるよう、経済的に安定している必要があるためです。ただし、収入が少なくても資産状況が確認できれば、身元保証人になれる場合もあります。
身元保証人になるのは、家族などの親族であるケースが多いです。しかし、近年は親子関係が疎遠であったり、子どもが引きこもりの傾向があったりして、子どもを身元保証人にできないことも珍しくありません。その場合、条件さえ満たしていれば、友人や知人でも身元保証人になってもらうことは可能です。
なお、身元保証人の有効期限は一般的に3〜5年(最大5年)とされている点も留意しておきましょう。
身元保証人がいないときの対処法
身元保証人がいない場合は、身元保証会社(身元保証サービス)を利用するのもひとつの方法です。
身元保証会社とは、事前に身元保証契約を締結しておくことで、親族に代わって身元保証を担ってくれるシステムです。これにより、身寄りのない高齢者でも病院や施設を安心して利用できます。
総務省の調べによると、一人暮らしの高齢者数は令和2年には672万人となっており、今後も増加することが予測されています。身寄りがない高齢者は決して少なくない状況です。
また、総務省が、埼玉県・東京都・神奈川県の10市区町村を対象に行った「高齢者の身元保証に関する調査」によると、9割以上の病院や施設で利用者に対し身元保証人を求めていることがわかりました。
上記10の市区町村では、身元保証人がいない場合、以下のような対応がとられています。(※1)
| 対応方法 | 割合 | 該当する病院・施設数 |
|---|---|---|
| 入院・入所させる | 3.5% | 31病院・13施設 |
| 入院・入所を断る | 15.1% | 28病院・161施設 |
| 個別に対応 | 60.3% | 363病院・393施設 |
| 成年後見制度・身元保証会社の利用を求める | 15.6% | 39病院・156施設 |
全471病院・782施設を対象(複数回答あり)
多くの病院では個別の対応となっているものの、成年後見制度、身元保証会社などの利用を求める病院や施設も一定数あることがわかります。
身元保証会社を利用する際には、「みもとら」をぜひご検討ください。みもとらでは、安心できる3つのサポート(基本契約・生活支援・死後事務支援)がパッケージ化されており、状況に合わせて選択できます。

契約時に預託金を預けていただくことで、亡くなった後の事務支援をサポートいたします。病気やケガによる入院や手術、施設への入所などに備え、身元保証を頼める親族がいない方は、まずはみもとらにご相談ください。

身元保証人に関するよくある疑問
ここでは、身元保証人に関する、よくある疑問に回答していきます。
身元保証人がいない場合はどうすればいいですか?
身元保証人がいない場合は、以下の方法の中から可能なものを探すと良いでしょう。
- 身元保証人が不要の病院や施設を探す
- 成年後見制度を利用できる病院や施設を探す
- 身元保証会社を利用する
多くの病院や施設では身元保証人を必要とするのが一般的ですが、なかには必要としないところもあります。しかし、近隣や希望する病院・施設が該当するとは限らないため、利用できる可能性は高くはないでしょう。さらに、成年後見制度が可能な病院や施設は少ないのが現状です。
身元保証人がいないときは、必要なときに適切な対応をしてくれる身元保証会社の利用が現実的かつおすすめです。

身元保証人にはどんなリスクがありますか?
身元保証人には、損害賠償責任や金銭的な負担が生じるリスクがあります。
身元保証人は、次のような役割を果たすことが求められるのが一般的です。
- 緊急連絡先となる
- 生活上必要な手続きの代行をする
- 本人に代わって意思決定する
- 賠償や支払いの連帯保証人となる
- 荷物の引き取り
- 身柄の引き取りや葬儀の手配
とくに、身元保証している病院や施設で本人が費用を支払えない場合、連帯保証人として経済的なリスクを負うことになります。
身元保証人と身元引受人・連帯保証人・後見人の違いは何ですか?
身元保証人と身元引受人には、明確な定義の違いはありません。病院や施設によって、呼び方が異なることもあります。
しかし、連帯保証人や成年後見人との違いも含め、あえて違いをあげるとすると、それぞれ以下のような役割があると言えるでしょう。
| 種別 | 役割の違い |
|---|---|
| 身元保証人 | 保証先の債務責任を負う |
| 身元引受人 | 保証先の賠償に対する責任を負う |
| 連帯保証人 | すべての損害に対する債務責任を負う |
| 成年後見人 | 財産管理や身上監護を行う |
連帯保証人の役割は最も重く、すべての損害に対する債務責任を負います。また、成年後見人は財産管理や身上監護の責任を負います。なお、成年後見制度は本人が死亡すると契約は終了するため、死亡後の相続や事務手続き、葬儀などは含まれないのが一般的です。
まとめ
身元保証人は、その人の信頼性を高める役割以外に、金銭的な負担を強いられることもあるため、親族であっても頼みにくいものです。頼れる親族がいない一人暮らしの高齢者の場合、身元保証だけでなく万が一のときに手続きを頼める人がいない場合も、心配のタネとなることが多いです。
そういった状況の中、近年は身元を保証するだけでなく、日常生活から亡くなった後の手続きまでサポートしてくれる身元保証会社(身元保証サービス)に注目が集まっています。
東京ガスと業務提携契約を結ぶ株式会社ファミトラが提供する「みもとら」では、身元保証支援・生活支援・死後事務支援の3つのサポートをご提供しています。みもとらでは、本人の意思を尊重した身元保証人となるだけでなく、定期訪問や病院への付き添い、親族や友人への訃報なども行うことが可能です。
現時点で身元保証人を誰にするべきか決めかねている場合は、一度みもとらにご相談ください。

(※1)出典元:総務省 高齢者の身元保証に関する調査

 お金
お金